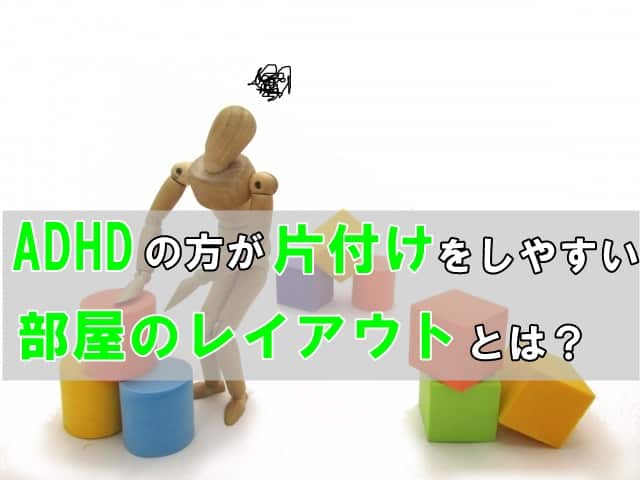将来的な移動手段を予想して補装具を検討する
身体障がい者にとっての移動手段はさまざまです。
歩くことが難しくても車椅子を使用すれば移動を行うことが可能ですし、外を歩くときに補助的な手段として杖を使用することもできます。
身体障がい者にとって移動手段を考えることは日常生活をおくるために必要不可欠です。
今回は身体障がい者にとっての移動手段について考えていきます。
車椅子や杖などの移動手段の役割について
~車椅子~
歩行を行うことが困難な場合に使用されることが多い。
自分で操作して移動をする場合と介助されて移動をする場合の2通りで移動を行うことができる。
歩行ができる方も外出時などの長距離の移動時に使用するケースもある。
(活用例)
脳性まひや脊髄損傷など幅広い疾患の方に適応になる
・家の中は短い距離なら杖歩行を行うことができるが、長距離の移動の時は車椅子を使用する
・家の中も外出時も車椅子を使用する など
※主に自分で座ることが可能な場合は、車椅子を使用することが多いです。
~電動車椅子~
自分で車椅子を操作することが難しい場合や座ることが難しい場合に、手元にあるスティックなどを利用して電動で移動することが可能な車椅子。
車椅子と言っても座位保持装置のように姿勢を支える機能があるものが多く、少ない力で手指の操作が可能であれば移動することができる。
ただ一般的な車椅子と比較して高価であり、重いことが難点。
(活用例)
筋ジストロフィーや脊髄性筋萎縮症、重度の脳性まひなどの姿勢保持が難しい方の場合に適応になることが多い
・家では普通型の車椅子を使用して長距離は電動車椅子を使用して外出する
・電動車椅子は持ち上げることが難しいので、車に乗るときはスロープなどを利用してそのまま乗り込む など
~杖(主にロフストランド杖)~
足に麻痺症状がある場合に手で体重を支えて補助的に歩行を行うときに使用する
比較的歩行が可能な場合により安全に実用的に使用することが多い
(活用例)
手よりも足に麻痺症状がみられる疾患(脳性まひの両麻痺など)や二分脊椎などの疾患が適応
・家の中は何も使用しなくても歩行を行うことができるが、外出時などの長距離を移動するときは杖を使用する など
~歩行器(PCWなど)~
杖では歩行が難しい場合に使用する
PCWは臀部背面での支持も可能なので、杖を使用して歩行するよりも支持が多くなる
(活用例)
杖歩行と同様に手よりも足に麻痺症状が見られる場合に適応になる
・家の中は杖歩行で移動、学校や外出時などは歩行器を使用する など
この他にも歩行器や車椅子を併用するなど、本人の状況に合わせて移動手段を確立していくことが大切です。
まとめ
移動を行うことは、普段の日常生活にとって必要不可欠な行動です。
身体に障がいがあってもなにかしらの移動手段を考えることは、社会で自立して生活していくために大切なことだと思います。
ただ障がいの程度は人それぞれ。
一人ひとりにあった移動手段を確立していきましょう。
※すべての身体障がい児の方が適応になるわけではありません。一つの考えとして理解していただけると幸いです。

出身地:宮崎生まれ鹿児島育ち
経歴:理学療法士/認定理学療法士(発達障害)
webライター
理学療法士として10年以上小児のリハビリに携わっています。
障がいをもった子どもたちとご家族の悩みはさまざまです。
少しでも悩みが解決できるようにこれからも情報を発信していきます!