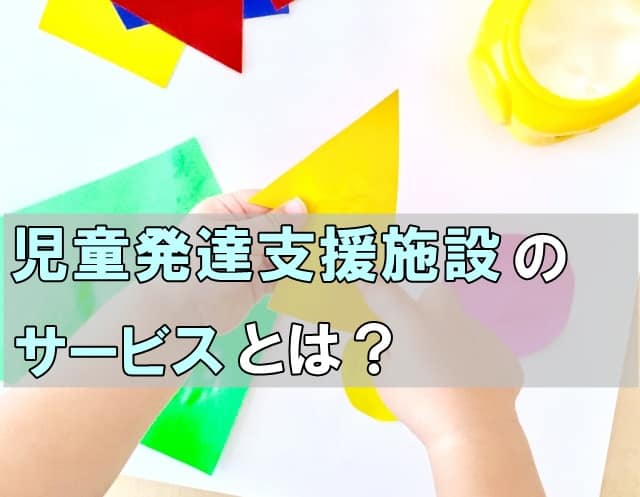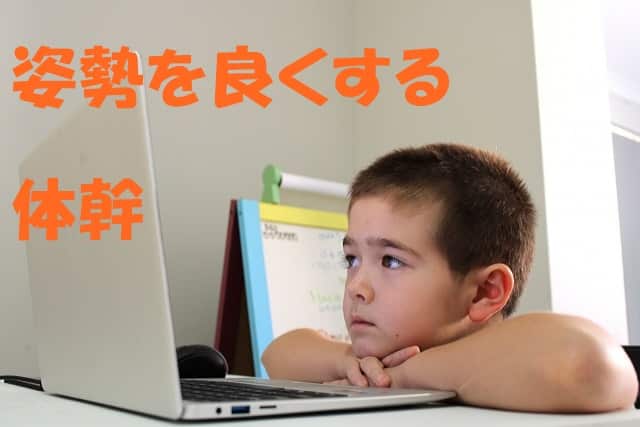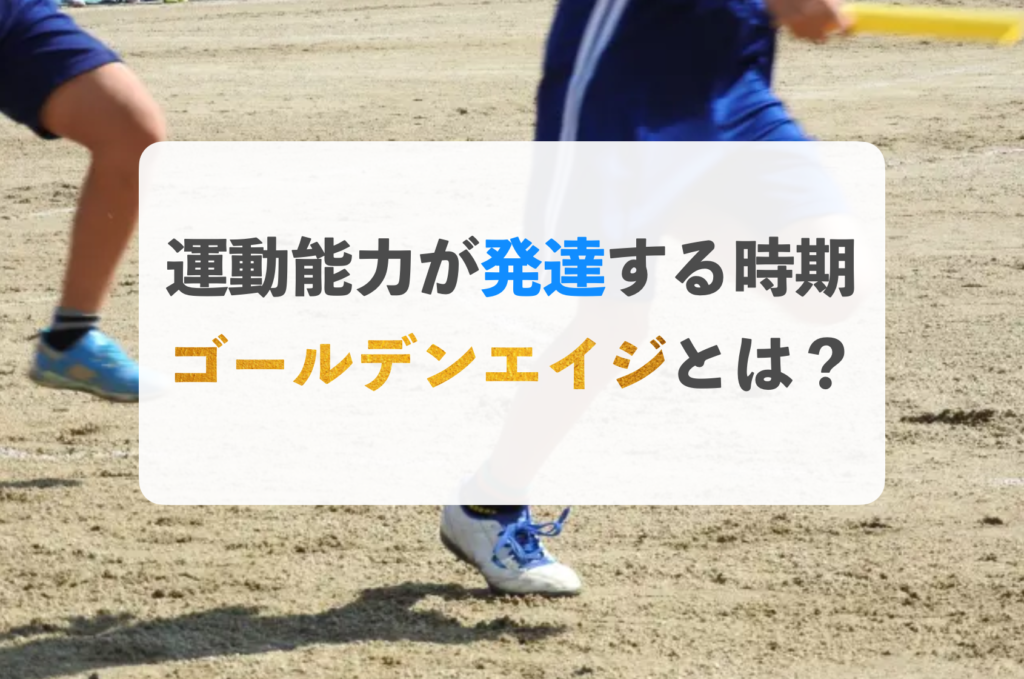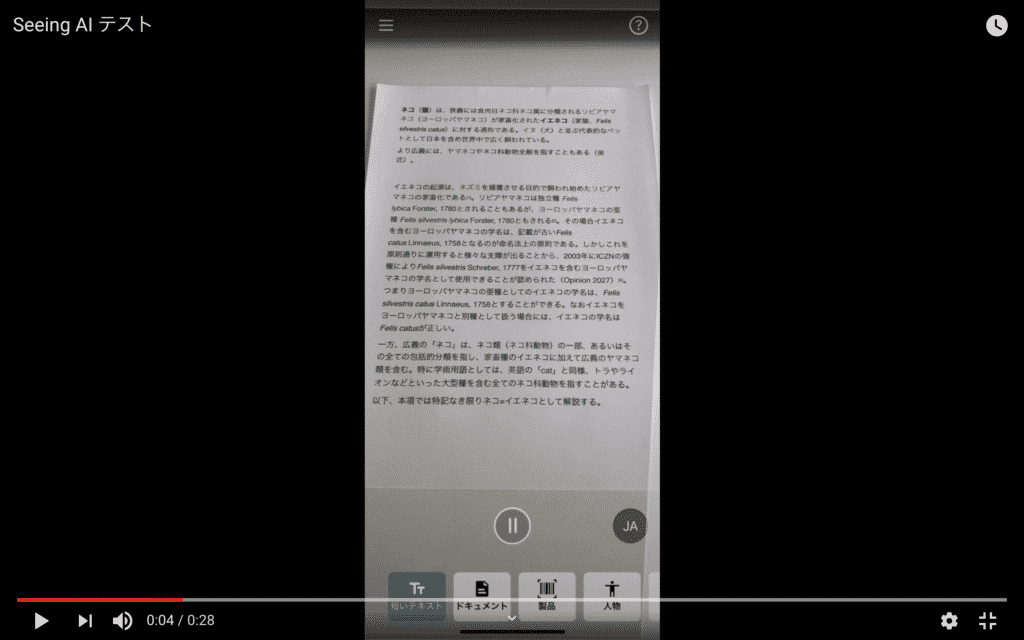将来の生活を予測しながら補装具を作製することが大事
障がい児の日常生活にとって補装具はなくてはならないものです。
移動を行う時は車椅子やバギーが必要ですし、座ることが難しい場合は座位保持装置が必要になります。
また、学校に通うようになると学校用の座位保持装置と家庭用の座位保持装置といった2つの補装具が必要になる場合もあります。
このように障がい児は年齢とともに状態や環境が変化することが特徴です。
そのため、補装具は身体障がい児の将来を予測しながら作製していくことが大切になってきます。
今回は、身体障がい児の将来を考えた補装具作製を行う重要性について考えていきましょう。
補装具と治療用装具の違いってなに?
まず補装具と治療用装具があることを知っておきましょう。
補装具とは?
補装具とは、基本的に日常生活でなくては困るものが当てはまります。
例えば身体障がい児の場合は家で過ごすために座位保持装置が必要ですし、移動を行うためには車椅子が必ず必要になってきます。
こういった「日常生活において必要と判断されるもの」が補装具です。
治療用装具とは?
治療用装具は、名前の通り治療中に必要な場合に支給されるものです。
例えば骨折をして短下肢装具が必要な場合は早急に着用しなければ効果は期待できません。
このようにできるだけ早く治療に装具が必要な場合に使用するのが治療用装具です。
補装具と治療用装具は申請方法が異なり、障がい児の場合の多くは補装具を申請していきます。
障がい児の場合は日常生活で必要になり長期間使用することが多いためです。
ただもちろん治療用装具を作成する場合もあるので、ケースバイケースで検討していきましょう。
将来を考えて補装具を申請するとはどういうことか?
障がい児の場合は補装具を申請することが多いですが、補装具の場合はより必要とする理由を明確にしなくてはなりません。
※治療用装具も同じように治療に必要な理由を考えなくてはなりません。
つまり車椅子がほしいからとか、もう一つ座位保持装置があると便利だなとかなんでもかんでも申請することは難しい場合が多いです。
今現在日常生活で困っていることを明確にして申請することが必要になります。
また、将来の生活を想定して補装具を揃えていくことも大切です。
例えば身体が小さいときは抱っこで移乗をすることができますが、年齢とともに身体が大きくなり抱っこをすることが難しくなります。
介助の仕方も抱っこから本人に支えてもらいながら移乗を行う必要性がありますし、介助の回数も少なくしなければ介助者の負担が軽減できません。
こういった成長とともに介助方法が変化することをできるだけ予測して補装具を申請することが大切です。
ただ、運動発達を予測することは簡単ではありません。
多くの場合は医療機関において医師・理学療法士などが関わっているはずなので、将来の生活について相談をしながら補装具の申請を行なうことが重要です。
まとめ
障がい児の補装具を考える時は、将来どのように生活が変化するのかということを予測することが必要です。
子どもは小さいままではなく身体も心も成長していきます。
時期に合った適切な補装具を使用できるようにしていきたいですね!

出身地:宮崎生まれ鹿児島育ち
経歴:理学療法士/認定理学療法士(発達障害)
webライター
理学療法士として10年以上小児のリハビリに携わっています。
障がいをもった子どもたちとご家族の悩みはさまざまです。
少しでも悩みが解決できるようにこれからも情報を発信していきます!