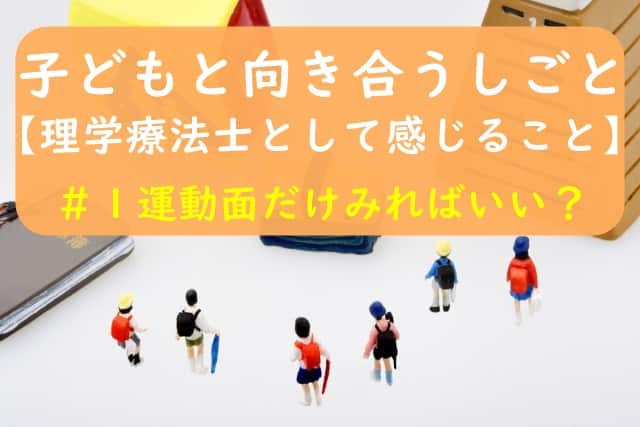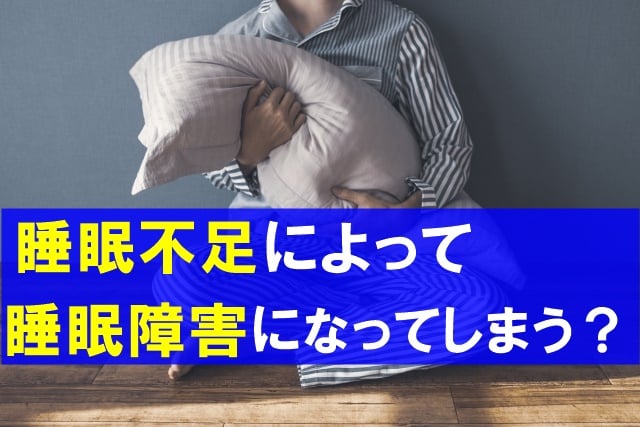障がいがあっても働くことが可能になってきた
障がい者の方にとっても働いて自立していきたいと考える方が多いのではないでしょうか。
以前までは障がいがあるというだけで働くこと自体が難しかったですが、現在は一般企業も一定数の障がい者を雇用しなければならなくなってきています。
多様な障がいがある方にとってさまざまな働き方があることは社会参加するために大切なことです。
ただ障がい者の方が働くことが社会に認められるようになってきたとはいえ、障がい者雇用と一般雇用にはどのような違いがあるのでしょうか。
今回は、障がい者雇用と一般雇用の違いについて紹介していきたいと思います。
障がい者雇用ってどれくらい雇用されるのか
一口に障がい者雇用と言っても全ての障がい者の方が好きな企業に就職できるわけではありません。
障がい者を雇用するために「障がい者雇用率」というものが決まっており、一定の従業員がいる企業はこれに従って障がい者を雇用する義務があります。
障がい者雇用の対象となる障がい
・身体障がい、知的障がい、精神障がい
法定雇用率
・従業員45.5人以上の民間企業の場合・・・障がい者雇用を2.2%行う
※令和3年4月までに雇用率は0.1%引き上げられ、従業員43.5人以上になっている
・国、地方公共団体などの場合・・・障がい者雇用を2.5%行う
・都道府県および市町村教育委員会・・・障がい者雇用を2.4%行う など
つまり従業員45.5人の民間企業の場合は、障がい者の方を1人雇用する達成義務があるということです。
これをどうとらえるか難しいところですが、障がい者雇用を促進するようになったと言ってもまだまだ少ないのが現状かもしれません。
障がい者雇用にはどのようなメリットがあるのか
障がい者雇用は基本的に手帳(身体障がい者手帳など)を所持していることが前提となる場合が多く、まだまだメリットが少ないと感じてしまうかもしれません。
ただ一般雇用と違うところはさまざまな障がいに配慮した就労形態を企業側が提供してくれることです。
雇用率が少ないとはいえ、自分の障がいの特性に合った配慮をしてくれれば継続して働きやすいですよね。
また企業と障がいについて話し合えることもメリットの一つです。
働き始めてからも働きにくく感じることは障がい者の方にとって多いはず。
そういった働き始めてからの働きにくさを随時相談しやすいことも障がい者雇用のメリットだと思います。
まとめ
障がい者雇用は障がい者の方が社会で自立して生活するために重要な制度です。
まだまだ雇用率は低く全ての障がい者の方に適応となる制度ではありませんが、雇用率も徐々に緩和されてきています。
多くの企業が積極的に障がい者を雇用することで、障がい者の社会的な自立が実現されることを期待したいですね!

出身地:宮崎生まれ鹿児島育ち
経歴:理学療法士/認定理学療法士(発達障害)
webライター
理学療法士として10年以上小児のリハビリに携わっています。
障がいをもった子どもたちとご家族の悩みはさまざまです。
少しでも悩みが解決できるようにこれからも情報を発信していきます!