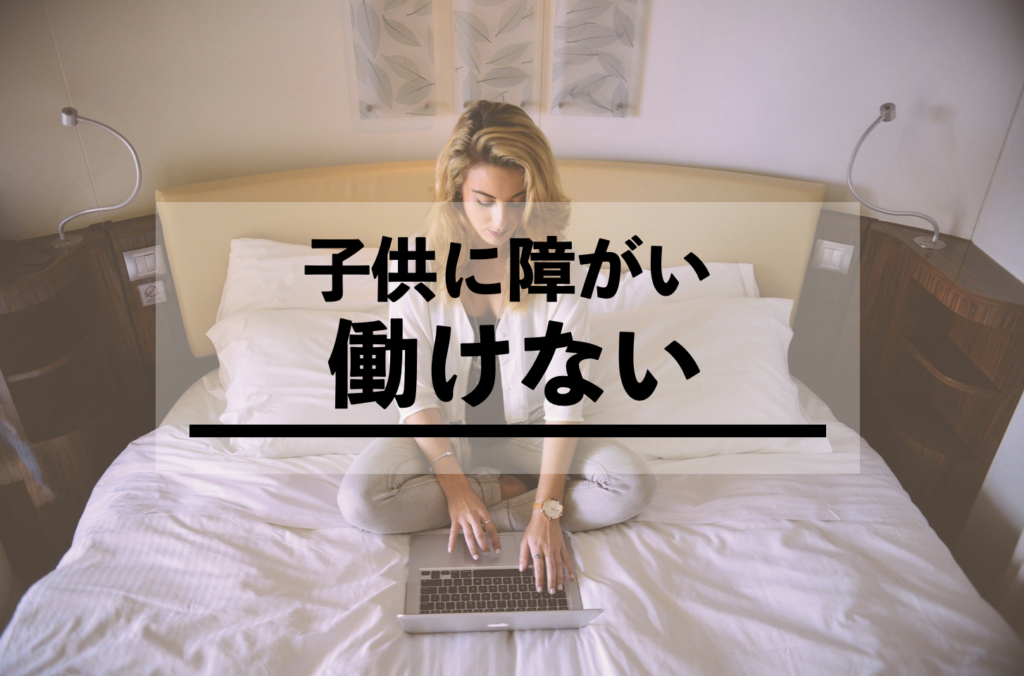障がい者にとって社会参加の障壁はまだまだ多い
日本も障がい者への理解が進み、障がいがあっても積極的に社会参加できるようになってきました。
ただ、それでもまだまだ障がい者が社会参加することは簡単ではありません。
今回は、障がい者が社会参加の障壁となるものについて考えていきましょう。
1 .物理的な障壁
物理的な障壁とは、段差や階段を始めとした環境面での障壁のことです。
例えば、車椅子の方であれば2階のオフィスに階段で昇ることが難しいので、就職することができないということもあります。
仕事の内容が充分に可能であっても、物理的な障壁により就職が困難というケースはまだまだあるようです。
こういった物理的な障壁を取り除くことを主にバリアフリーといいますが、最近はだれでも使用することができるデザインであるユニバーサルデザインという考え方も広まってきています。
多くの企業でバリアフリー化は進んできていますが、まだまだ障がい者の立場に立った視点で考えていかなくてはなりません。
2 制度的な障壁
制度的な障壁とは障がいが理由で資格取得が難しかったり、就学することが難しかったりすることです。
障がいの種類や程度によって資格取得の難しさは違いますが、まだまだ多くの資格が障がいの有無によって取得できません。
3 文化・情報面の障壁
文化・情報面での障壁とは、障がい者の方やそのご家族に必要な情報がいきわたらないということです。
例えば、障がいに適した支援やサービスがあったとしても、必要な情報を知らなければ支援やサービスを受けることができません。
現在はさまざまな福祉サービスが充実してきていますが、情報として障がい者の方と共有しなければ意味をもたなくなってしまいます。
情報は有益。
必要な情報が十分にいきわたるようにすることも大切です。
4 意識上の障壁
そして最後の障壁が意識上の障壁です。
この障壁が最も根強く残っている障壁であり、最も改善していかなくてはならない障壁かもしれません。
意識上の障壁とは、健常者の方や社会全体が障がいに対してイメージしている意識のことで、ある意味偏見とも受け取れる障壁です。
例えば脳性まひと言えば車椅子とか、自閉症スペクトラムと言えば育て方が悪いとかそういった偏見がまだあるのではないでしょうか。
脳性まひの方の症状も人それぞれで杖をついて歩くことができる方もいれば、車椅子に乗っていても生活している方も多いです。
自閉症スペクトラムも育て方が悪いのではなく、生まれつきの脳の機能的な障がいが原因であることが分かってきています。
こういった知識を社会全体が共有するだけでも、社会全体の障がいに対する意識は変わるはずです。
変わらなければならないのは私たちの意識なのではないでしょうか。
まとめ
社会全体で障がいへの理解が進み、多くの企業で障がい者の方を雇用する機会が増えてきました。
ただ、社会参加が進む一方でまだまだ障がい者の方は社会に対してさまざまな障壁と向き合っていかなくてはなりません。
障がい者の目線に立って私たち健常者が意識を変えなくてはなりませんね!

出身地:宮崎生まれ鹿児島育ち
経歴:理学療法士/認定理学療法士(発達障害)
webライター
理学療法士として10年以上小児のリハビリに携わっています。
障がいをもった子どもたちとご家族の悩みはさまざまです。
少しでも悩みが解決できるようにこれからも情報を発信していきます!