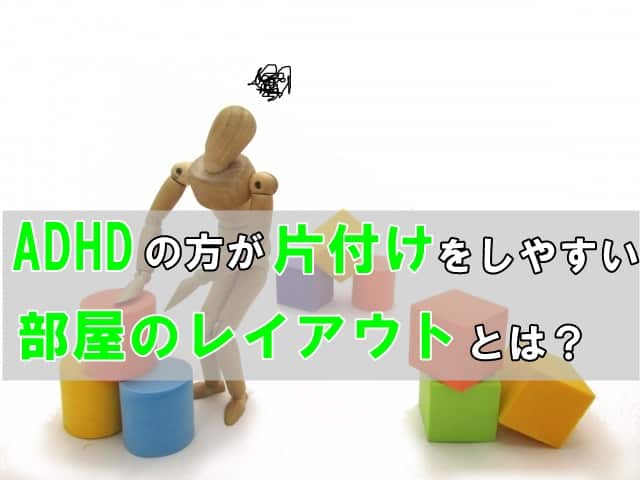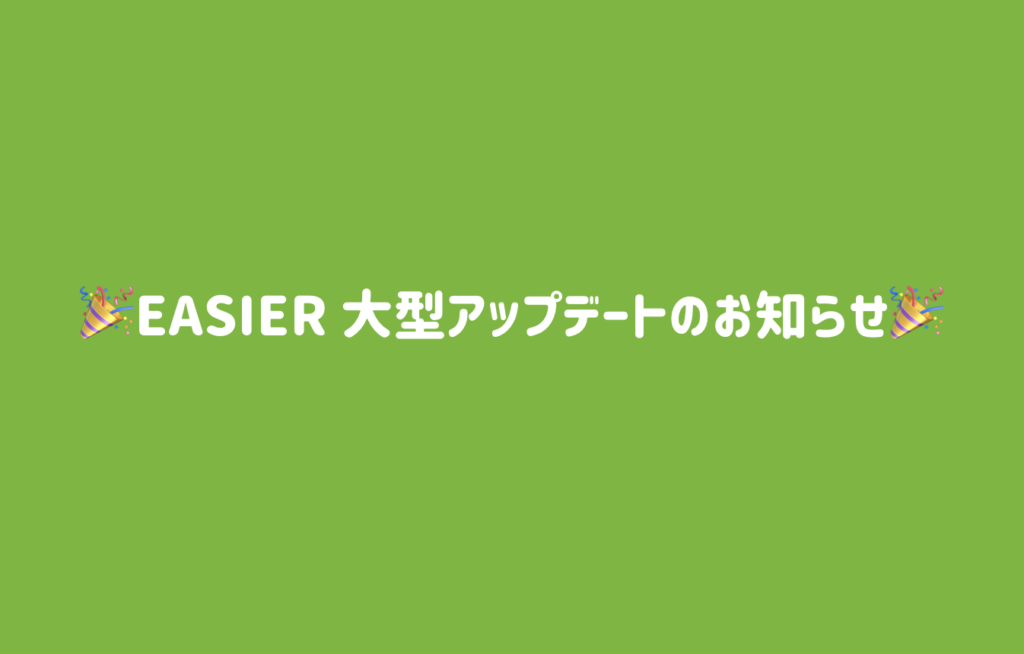目次
正常っていったいなに?
正常発達を知ることは子どもの発達に欠かすことが出来ない要素。
私も正常発達を学んでその知識や経験を活かして子どもたちと関わっているので、大切な知識であると感じています。
治療をしている中ご家族の方もやはり正常に発達してほしいという思いがあるようです。
誰しも自分の子どもは正常に発達してほしいと思うもの。
当然の感覚なのかなと感じます。
ではそもそも正常っていったい何なのでしょうか。
今回は障がいをもった子どもたちにとっての正常とはどのような意味をもつのか、ということについて考えていきます。
そもそも正常ってどういう意味があるのか
正常の本来の意味は、「正しい状態にあることや普通であること」という意味があるようです。
障がいをもった子どもたちに当てはめてみると、障がいがあることは正しい状態になく普通ではないという風にも捉えられます。
ただ障がいをもった子どもたちの状態を普通であると考えるとありのままを受け入れて、その子らしく生きていくことと前向きに捉えることができるはずです。
健常者の状態を正常としてしまうと、本来持っている子どもたちの良さを否定することになってしまいます。
私たち健常者の意識を変えて、障がいがあっても社会に参加・貢献できるようにすることが大切なのかもしれません。
正常にとらわれすぎると大事なことが見落とされてしまう
子どもたちと関わるうえで正常発達の知識は大切です。
でも、障がい児は正常に発達すること自体が困難である場合がほとんど。
子どもたちは子どもたちなりのやり方がありますし、達成感の感じ方も違います。
例えば、身体をうまく動かすことが難しい子であれば寝返りができるようになっただけでも相当な努力が必要なはず。
寝返りのしかたは反り返りながら行うかもしれませんが、それは本人なりに懸命にやろうとしている動作なのです。
寝返りのしかたを正常に近い形で行おうとすると、子どもは自信をなくしてしまうかもしれません。
正常にこだわるよりもまずは自分なりに動けるようになること。
これが障がい児と関わるうえで大事なことだと思います。
正常発達はなにも運動だけではない
正常発達をしていくためには運動だけが注目されてしまいがちです。
でも、発達は運動だけ発達していくわけではありません。
心と身体は大きな関わりがあり、知的な発達が促されることにより運動も発達していきやすくなります。
身体を含めた運動面だけ発達していくわけではなく、さまざまな発達を考えながら関わっていくべきです。
まとめ~障がい児と関わるときは正常にこだわりすぎないようにしよう~
・正常発達は健常者の発達であり、障がい児全てに当てはまるわけではない
・健常者も個性があるように障がい児にもそれぞれ個性がある
・障がい児なりの運動の行い方を認め、その運動から発達をサポートしていく
・正常を押し付けるのではなく、子どもたちの長所を認めることが重要
正常について考えることは難しく、答えがないことなのかもしれません。
障がいをもっていても自分なりに生活していけるような環境が整って初めて「正常」な状態です。
まずは障がいに関しての社会の意識を変えていくことが必要ですね。

出身地:宮崎生まれ鹿児島育ち
経歴:理学療法士/認定理学療法士(発達障害)
webライター
理学療法士として10年以上小児のリハビリに携わっています。
障がいをもった子どもたちとご家族の悩みはさまざまです。
少しでも悩みが解決できるようにこれからも情報を発信していきます!