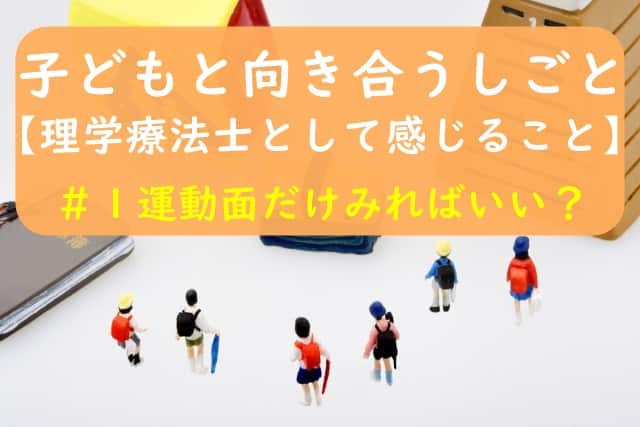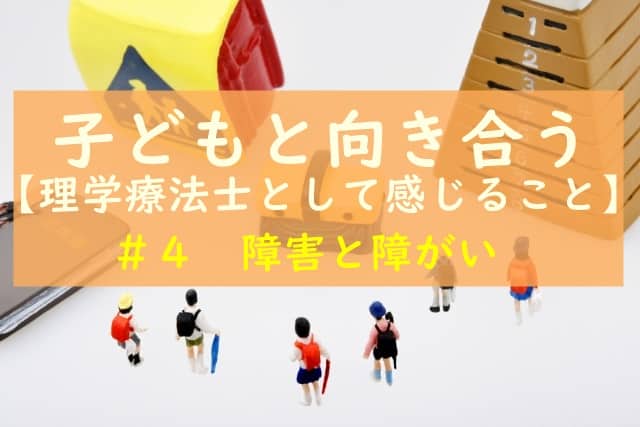
「障害」という表現を何気なく使っていないか
普段から障がいをもった方々に関わっていると、「障害」という表現は正しいのか?ということを考えさせられます。
日本ではあまりにも社会全体に障害という表現が定着しているためか、私たち健常者は当たり前のように「障害者」とひとくくりに表現しているのではないでしょうか。
当たり前のように教えられてきたので言葉の意味をよく考えずに使ってしまっているのも確かです。
「障害者」という表現の受け取り方は個人によって違うと思いますが、人によっては差別的な扱いを受けているように感じてしまうかもしれません。
実際患者さんの中でも障害者と言われることが嫌という方も多いです。
こういった背景から最近は社会に対して害があるわけではないということで「障がい者」という表現が多くなってきました。
ただ、患者さんによっては逆に「障がい者」と呼ばれる方にむしろ嫌悪感があるという方もいらっしゃいます。
捉え方は人それぞれなので、障がい者と表現されることでむしろ差別的な扱いを受けている印象をもたれるようです。
これを聞いて確かにそう感じることも間違いではないなと思います。
今まで障害者と表現されていたのに、いきなり障がい者と表現するとかえって際立ってしまいます。
そもそも障がい者とひとくくりにまとめて表現することも間違いではないでしょうか。
障がいにもさまざまな障がいがあるわけで、身体に麻痺があったりコミュニケーションが上手くできなかったり、内臓機能に問題があったりしても同じように障がいとされます。
健常者でも糖尿病だったり痛風になったりしますが、ひとくくりに障がい者とは言われません。
健常者と障がい者のラインはいったいどこにあるのか。
なんだか健常者の私たちが都合よくまとめて障害者と当てはめてしまっているような気がします。
大切なことは障がい者への理解と、社会全体が障害・障がいという言葉の意味をもう一度考え直すこと。
健常者も健康が日常的ではないのですから。
ある意味では私たちも同じ障がい者なのです。
どういう表現が正しいのか
障害の意味
ものごとの達成や進行のさまたげとなること、また、さまたげとなるもののこと。
障碍の意味
元は仏教用語。明治時代前までは「しょうげ」と呼ばれていたが、障害の普及とともに使われなくなってきた。
障がいの意味
「害」という字が危害や公害などの負のイメージがあるということ。障害者は害があるわけではないということなどから表記を改めたもの。
障がい者はどのように表現したらよいのでしょうか。
障害や障がいという言葉が相手を不快にするのならば、表現の仕方を変えなければなりません。
「障害」という表現が嫌な人もいるでしょうし、「障がい」という表現でも嫌な人もいると思います。
私が思うにまず相手の個人を尊重すること。
そして、相手の立場に立って表現を変えていく必要があるのではないかと思います。
まとめ
今回は「障害」という表現について考えてみました。
現在はコロナウィルスが流行していますが、コロナウィルスにかかっても差別の対象になってしまうのは悲しいことです。
障害という表現も同じように人によっては差別に感じることがあると思います。
一人ひとりが相手の立場に立って考えられるようにしていきたいですね。

出身地:宮崎生まれ鹿児島育ち
経歴:理学療法士/認定理学療法士(発達障害)
webライター
理学療法士として10年以上小児のリハビリに携わっています。
障がいをもった子どもたちとご家族の悩みはさまざまです。
少しでも悩みが解決できるようにこれからも情報を発信していきます!