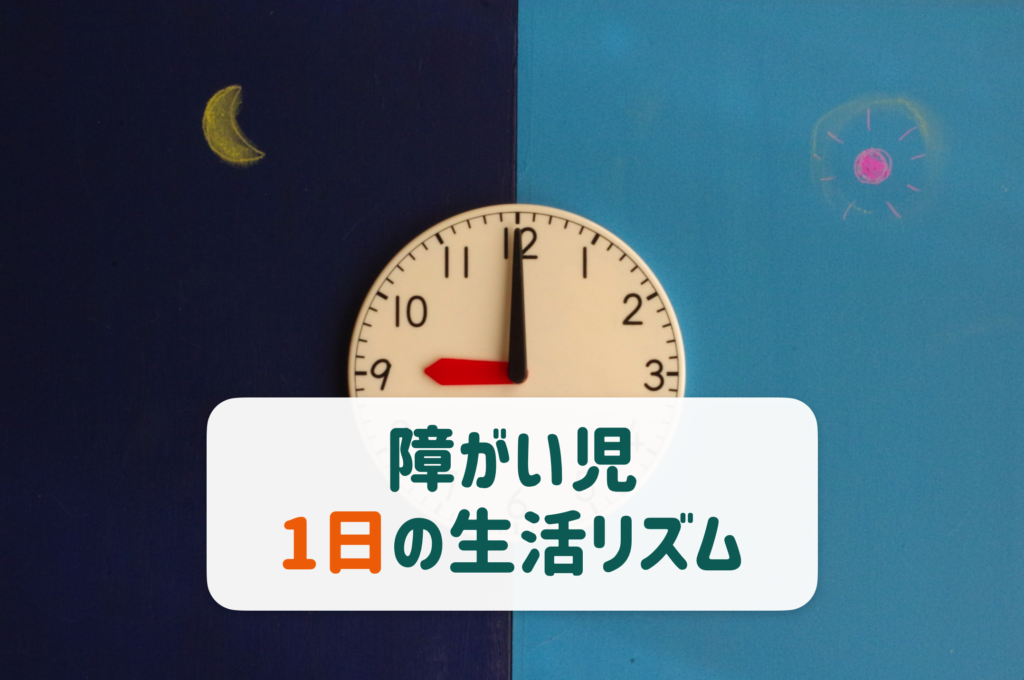
障がい児は生活リズムがくるいやすい?
多くの方は決まった時間に起きて日中活動をして、決まった時間に就寝すると思います。
そのため自然に朝起きて活動し、夜寝るという1日のリズムはだれしも同じはずです。
でも、最初から1日のリズムが整っているわけではありません。
大人は昼寝をしなくても大丈夫ですが、多くの未就学児は毎日まとまった昼寝をすることが特徴です。
このように年代によって一日のリズムが違い、大人になるにつれてだんだんと1日のリズムができていきます。
では障がい児の場合はどうなっているのでしょうか。
今回は障がい児と一日のリズムの関係について考えていきます。
赤ちゃんの時期はまだ生活のリズムが整っていない
赤ちゃんはまだ一日の生活リズムが整っていないので、寝たり起きたりを繰り返すことが特徴。
例え夜であっても2~3時間おきに寝たり起きたりを繰り返すので、育児は思っている以上に大変です。
おそらくほとんどの子育て経験者の方々は自分の時間なんてなかったのではないでしょうか。
ただ多くの場合が生後3か月を過ぎると自然に朝起きて夜寝るという習慣が少しずつ形成されていきます。
子どもの生活リズムができてきても育児が大変なことに変わりはありませんが、少なくともずっと睡眠不足が続くことはないでしょう。
このように子どもの1日のリズムを整えることは家族の日常生活にも大きく影響するのです。
障がいがあると1日の生活リズムが整いにくい?
それでは障がいがある子どもたちの生活リズムはどうかというと、やはり生活習慣が崩れやすい傾向があるように感じます。
よく眠れなかったり、逆に1日の大半を寝てしまったりなど、日中の活動に大きく影響することが多いです。
子どもの生活のリズムが崩れると、家族の生活のリズムも崩れてしまいやすくなります(その逆もあります)。
ではどうして障がいがあると一日のリズムが崩れてしまいやすいのでしょうか。
・身体的な影響がある
全身の筋緊張が高いと姿勢が安定しにくいので、睡眠が妨げられるなど
・発達障害の可能性
感覚過敏や気持ちの切り替えが苦手などの原因で寝つきが悪くなる
二次障害としてうつ病などになってしまい、睡眠が障がいされるなど
生活リズムを整えるために必要な3つのポイント
①毎日決まった時間に起きて、朝食をしっかり食べる
夜更かしをしてもできるだけ同じ時間に起きるようにしましょう。
また、朝日を浴びて体内時計をリセットすることも大事。
朝食はバナナ1本でも良いので、必ず食べるようにすると午前中の活動がスムーズになります。
②昼食を食べて、昼寝は3時までに15分程度
昼食を食べて1時間前後は眠くなりやすい時間。
眠気で活動がさまたげられる場合は、15分ほどの仮眠が効果的です。
ただ3時以降の遅い時間や長い仮眠は夜の睡眠を妨げてしまうので注意が必要。
③夕方に軽い運動、夕食と入浴は早めに
夕方の軽い運動は睡眠の質を高めます。
逆に、就寝する直前に夕食や入浴をすると寝つきが悪くなってしまいます。
できるだけ早い時間に済ませて、就寝までリラックスするようにしましょう。
まとめ~できるだけ昼は活動をして夜は休めるように工夫を~
生まれてから数年は寝る時間が多く、一日の生活のリズムを作っていく大事な時期です。
それは障がいがあっても同じで、できるだけ規則正しい生活をすることが日中の活動のパフォーマンスに大きく影響します。
一日のリズムを整えて毎日元気に過ごせるようにしましょう!

出身地:宮崎生まれ鹿児島育ち
経歴:理学療法士/認定理学療法士(発達障害)
webライター
理学療法士として10年以上小児のリハビリに携わっています。
障がいをもった子どもたちとご家族の悩みはさまざまです。
少しでも悩みが解決できるようにこれからも情報を発信していきます!













