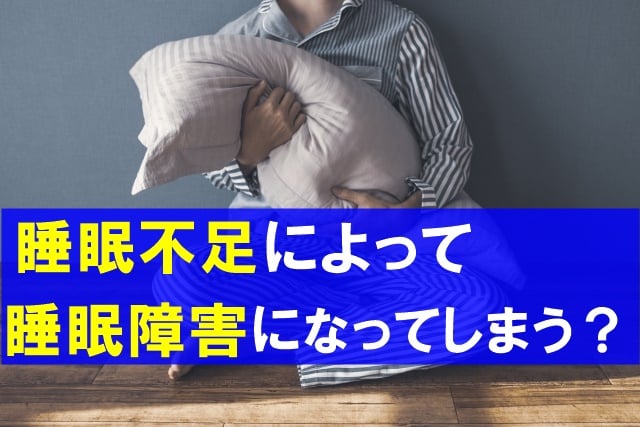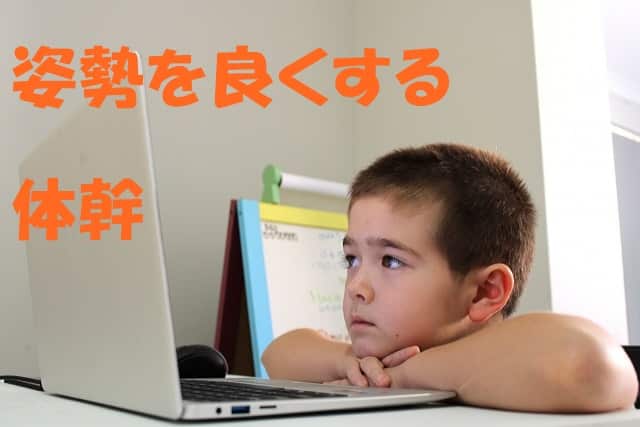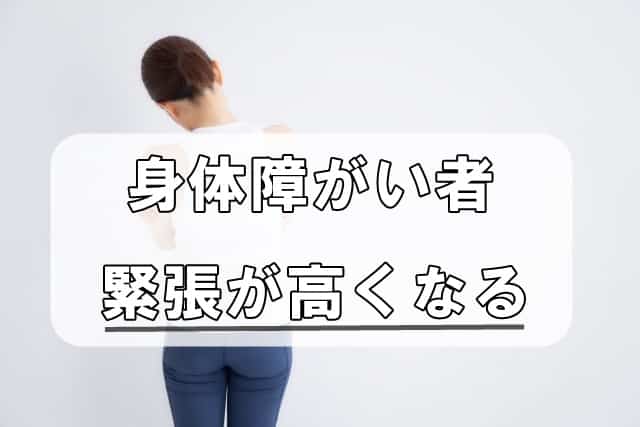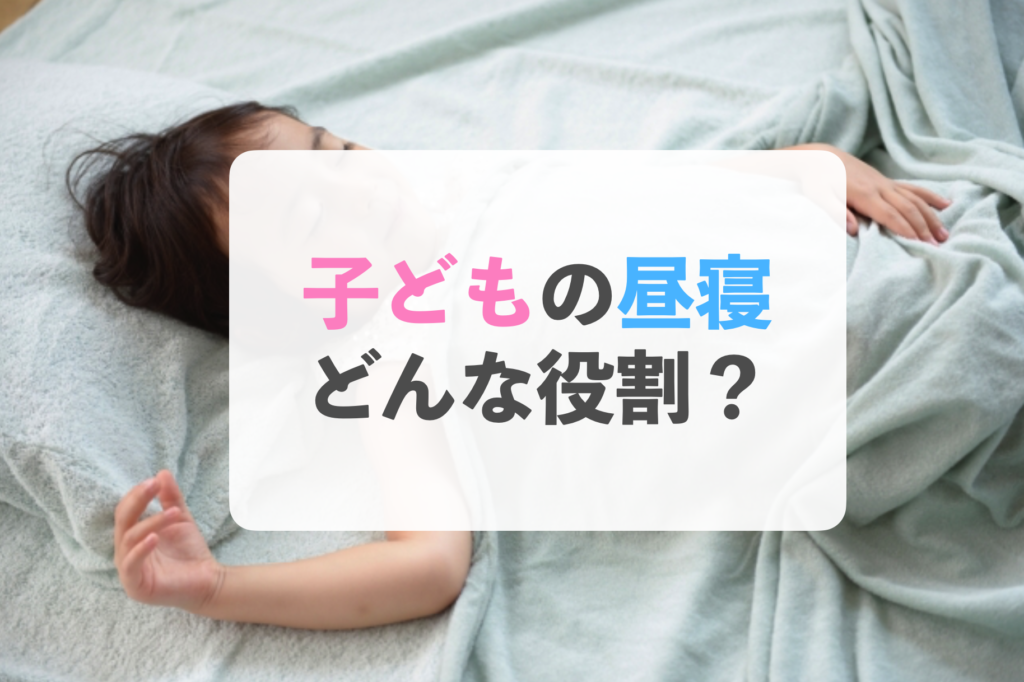
子どもは昼寝をすることで成長していく
子どもの昼寝は大人と違って長いですよね。
毎日1~2時間昼寝をしても夜は大人と同じぐらい寝るかもしくはそれ以上かもしれません。
でも、子どもの昼寝はなぜ大切といわれているのでしょうか。
今回は子どもの時期の昼寝の役割について考えていきましょう。
最初は一日のほとんどを寝て過ごしている
赤ちゃんって一日中寝ているのかというぐらいよく寝ますよね。
そうですね。
でも少しずつ起きている時間が長くなってくることが特徴です。
子どもの睡眠時間についてまとめていきますね。
~月齢ごとの平均睡眠時間~
新生児(生後1~3ヵ月ごろ)
15~17時間。ただ、大人と同じように夜にまとまって寝るのではなく、日中も寝ていることが多い
生後6か月~7ヵ月ごろ
11~14時間。このころになると日中の昼寝の時間が短くなり、夜にまとまって寝る時間が増えてくる
生後1歳ごろ
11~14時間。日中の昼寝の時間がさらに少なくなり、夜にまとまって寝るというリズムがついてくる。
昼寝は午後の一回になる場合が多い。
3歳ごろ
11~12時間。ほとんどの子どもたちが午後の食後一時間程度昼寝をする。一日の活動内容によっては夕方に寝てしまうこともある。
5歳~6歳ごろ
8~10時間。このころになると昼寝をしなくても活発に日中活動をすることができるようになる。ほとんどの子どもたちが昼寝をしなくなる。
ただ夜寝る時間は大人よりも長い。
このように小学校に入学する前にはほとんどの子どもたちがお昼寝をしなくなります。
夜の睡眠時間だけでも日中に活動できるようになるということですね!
どうして子どもの時期は昼寝が必要なのか
でもどうして子どもの時期だけ昼寝が必要なのでしょうか。
詳しくは分かっていませんが、子どもの成長と大きく関わりがあると言われています。
1 体力がまだ十分ではないから
子どもの時期は活発に身体を動かして急激に成長していく段階にあります。
ただまだ一日中活動するためには体力が十分ではないため、夜の睡眠だけでは足りないことも。
2 夜の良質な睡眠のために昼寝が必要だから
夜の睡眠は心身の成長のために活発に成長ホルモンが分泌されます。
適切な時間に昼寝をすることで夜にまとまって寝ることができるようになるので、結果的に夜の良質な睡眠が促されていきます。 など
なるほど。
昼寝はまだ一日のリズムができていない子どもにとって重要な役割があるのですね。
そうですね。
でも一人ではまだ上手く寝付くことができない場合が多いので、昼寝に関わらず夜も大人が一緒に寝かしつけをすることが大切です。
保育園や幼稚園だけではなく、家庭の環境も整えるようにしていきましょう。
まとめ
お昼寝は、まだ子どもの生活のリズムが形成されていない時期にとって確保しなければならない大切な睡眠時間です。
ただ、あまり寝すぎてしまうことも生活のリズムが崩れてしまいます。
大切なことは日中活動をしっかり行えているのか。
そして、夜にまとまって寝ることができているかということです。
子ども一人一人に合った生活のリズムは違うので、子どもにあった睡眠リズムをつけるようにしていきましょう!

出身地:宮崎生まれ鹿児島育ち
経歴:理学療法士/認定理学療法士(発達障害)
webライター
理学療法士として10年以上小児のリハビリに携わっています。
障がいをもった子どもたちとご家族の悩みはさまざまです。
少しでも悩みが解決できるようにこれからも情報を発信していきます!