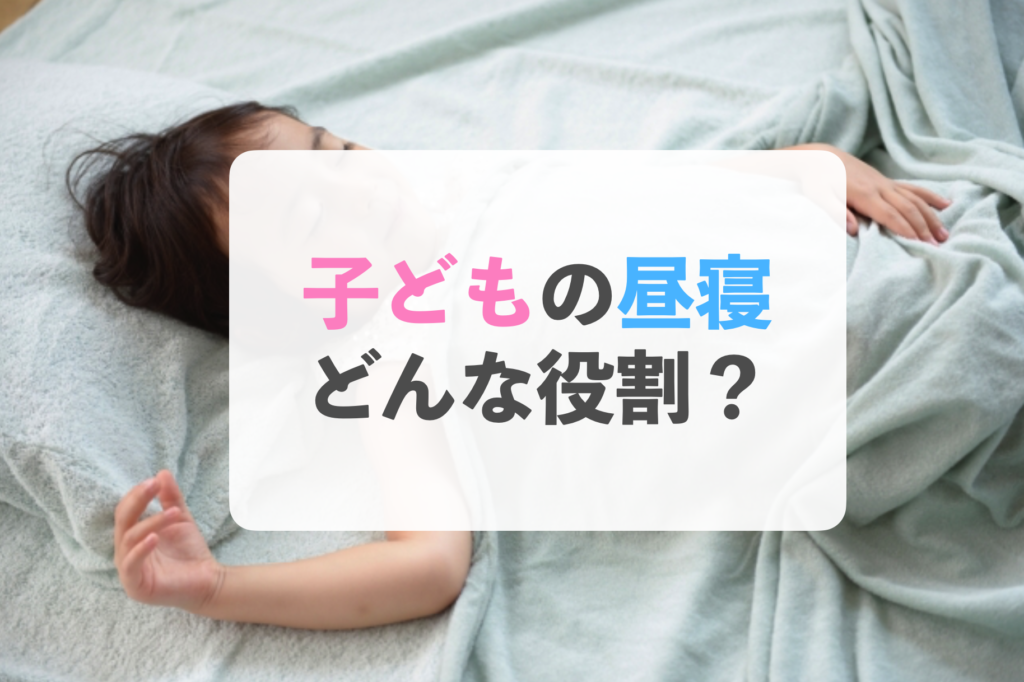股関節の脱臼は肢体不自由児の筋緊張に大きく関わっている
脳性まひをはじめとした肢体不自由児は、股関節が脱臼しやすい傾向があります。
肢体不自由児は四肢の筋緊張が高く、限られた身体運動が多いため股関節への影響が大きいためです。
また、健常者と同じように立って歩くといった股関節への荷重経験が少ないことも脱臼してしまいやすい原因の一つ。
では、股関節が脱臼すると身体にどんな影響があるのでしょうか。
また、脱臼を予防することはできるのでしょうか。
今回は、肢体不自由児と股関節脱臼との関わりについて考えていきたいと思います。
股関節が脱臼するとからだにどんな影響があるのか
股関節は身体と下肢をつなぐ重要な関節です。
そのため脱臼してしまうとからだにさまざまな影響がみられます。
股関節は身体の中でも大きな関節で
身体を支えるなどの大切な機能があります。
以下に股関節が脱臼したときの影響についてまとめていきますね!
・立つ、歩くといった身体運動が制限される
・痛みが発生する
・側弯のリスクが高まる
・脱臼していない股関節への負担が大きくなる
・日常生活動作が困難になる など
確かに、子どものころは少ないながらも立ったり歩いたりする練習をしていました。
そのおかげか分かりませんが、股関節が脱臼するなんてことはありませんでしたが・・・
中学生から大人にかけてからだが成長してきたせいか、以前のように立つことが難しく股関節も痛みがでてきました。
股関節の脱臼は、立ったり歩いたりするときに最も影響が大きくなります。
動くたびに痛みがあると大変ですよね。
大事なことは脱臼を予防していくことです。
脱臼を予防することはできるのか
股関節は一度脱臼をしてしまうとなかなか元のように戻すことは難しいです。
そのため、脱臼をしないように予防することが重要になります。
脱臼の最も大事な治療は「脱臼をできるだけ予防」することです。
肢体不自由児のお子さんが脱臼を予防するために必要なことをまとめていきます!
・できるだけ早期から立位、歩行の経験を積む
・定期的に整形受診を行う(股関節の状態をチェックする)
・股関節を外転、外旋位(あぐらのような状態)で保つ時間を増やす
・立位台、歩行器などの補装具を活用する など
麻痺があるとどうしても足がはさみ状に突っ張ってしまいます。
その状態が続くと股関節が脱臼しやすくなってしまうので、できるだけ足を開いた状態にして股関節に荷重することが必要です。
立ったり歩いたりする機会が少ないことでも脱臼しやすくなってしまうのですね。
普段の生活の中で意識して立つ機会を増やすことも重要ですね!
一人で立つことが難しい場合も、立位台や歩行器などの補装具を使用すれば立ったり歩いたりする経験はできます。
脱臼してしまうと日常的に痛みがでてしまうなどのデメリットは多いので、できるだけ予防することが大事です。
まとめ
股関節の状態は、子どもの時はまだ十分に形成されていません。
しかし、歩けるようになり股関節に荷重経験が増えることで関節がしっかりしてきます。
肢体不自由児も股関節への荷重経験を増やすことで脱臼をできるだけ予防することが大切。
身体が小さいうちから立つことや歩く経験を積極的に行いましょう!

出身地:宮崎生まれ鹿児島育ち
経歴:理学療法士/認定理学療法士(発達障害)
webライター
理学療法士として10年以上小児のリハビリに携わっています。
障がいをもった子どもたちとご家族の悩みはさまざまです。
少しでも悩みが解決できるようにこれからも情報を発信していきます!