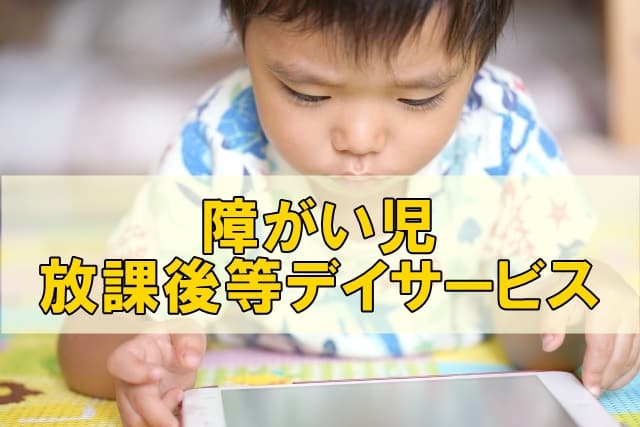
放課後等デイサービスは障がい児の成長に必要なサービス
最近は共働きが増えてきた影響で、放課後に学童を利用する家庭が多くなってきています。
一方障がい児の場合はどうかというと、これまでは放課後に安心して預けられるサービスは限られていました。
そういった背景から平成24年に障がい児が安心して過ごすことができる環境を提供するために「放課後等デイサービス」という事業が始まっています。
放課後等デイサービスは、ただ単に放課後に預けられるというだけではなく障がい児の成長にとっても必要なサービスです。
今回は放課後等デイサービスとはどういったさーぶすなのかということについて考えていきたいと思います。
放課後等デイサービスはただ預けるためだけのサービスではない
放課後等デイサービスは、6歳~18歳までの障がいのある子どもたちが放課後や夏休み・冬休みなどの長期休暇に利用できる福祉サービスです。
子どもたち一人一人にあった関わり(療育)や集団での活動を経験し、家庭と学校以外の場所で友達と関わることができるので、学童と似たようなサービスとも言えます。
ただ、障がい児の場合はより専門的な関わりが必要です。
そのため学童と違って将来のための自立支援と日常生活に役立つ活動を行っていきます。
個別で支援内容が変わるので、その子にあった支援をしてくれることが魅力ですね!
放課後等デイサービスは障がい児にとって大切なサービスです。
毎日の生活の中でぜひ活用していきましょう!
子どもにあった支援とはどんな内容なのか?
厚生労働省の「放課後等デイサービスガイドライン」によると、以下のようなサービス内容となっています。
・将来的な自立を支援することと日常生活の充実のために活動を行う
・子どもたちの発達過程にあった創作活動を行う・生活している地域との交流の場を設ける・同年代の子どもたちと同じように余暇活動を経験する
このように障がいをもっていても子どもたちらしく日常生活を行うことができるように配慮されています。
つまり、放課後等デイサービスは療育の視点で障がい児と関わっていくということですね。
でも、障がい児であればだれでもサービスを受けられるわけではないですよね?
地域によって違いはあるので一概には言えませんが、基本的には6歳から18歳までの就学している子どもたちで、障害手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などの手帳を所持していればサービスを受けることができます。
または、発達上の特性があり特別な配慮が必要で医師の診断書がある子どもたちも受けることができる場合があるようです。
でも、放課後等デイサービスを利用する必要性は考えなくてはなりません。
まとめ
これまで障がい児は特別な支援が必要なことから学校以外で社会経験を積むことが困難でした。
放課後等デイサービスは学校以外で友達との関わりや、自立支援などのサービスを受けることができるサービスで、障がい児にとって社会を経験する大切な場所だと思います。
ただ預ける場所ではなく、成長を促し日常生活を充実したものにしていく場所として放課後等デイサービスはさらに重要度が増していくのではないでしょうか。

出身地:宮崎生まれ鹿児島育ち
経歴:理学療法士/認定理学療法士(発達障害)
webライター
理学療法士として10年以上小児のリハビリに携わっています。
障がいをもった子どもたちとご家族の悩みはさまざまです。
少しでも悩みが解決できるようにこれからも情報を発信していきます!












