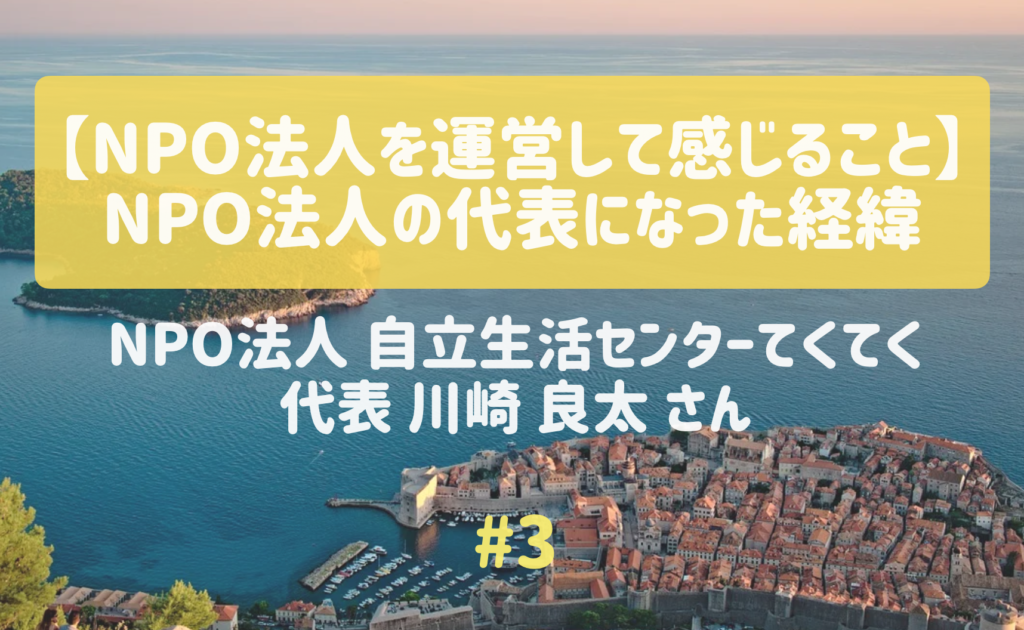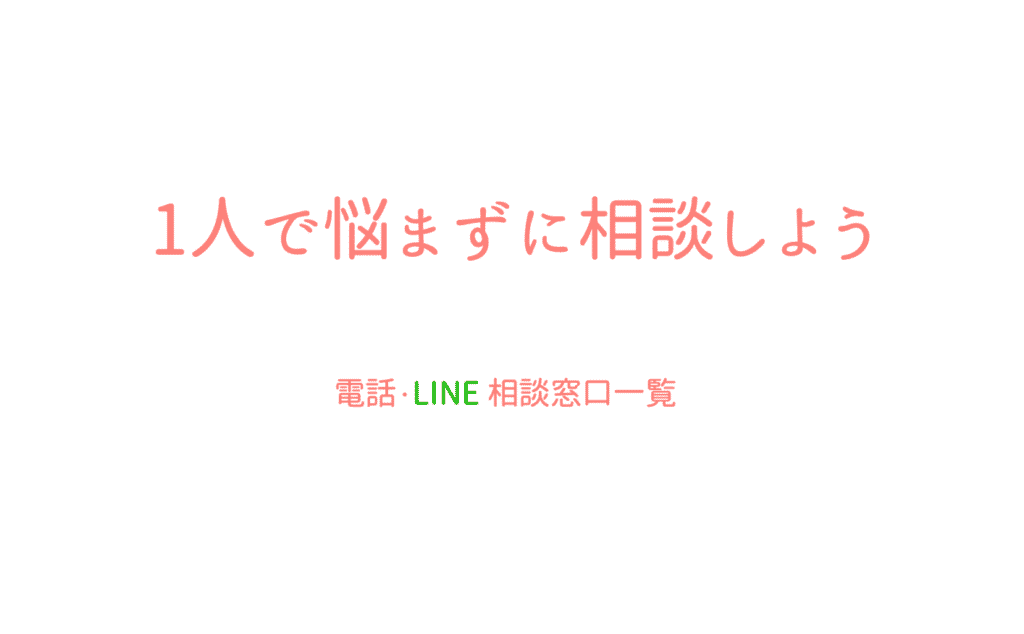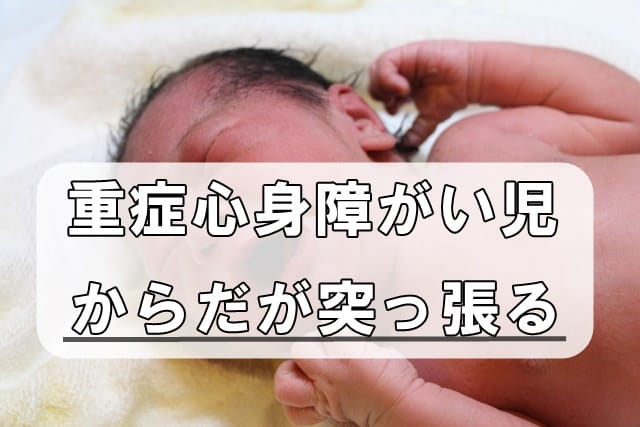目次
今回の記事では障がい者の英語表現についてご紹介します。一概に障がい者といっても様々な表現方法があります。それぞれのニュアンスの違いまで詳しくご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
障がい者を英語で言うと?

障がい者を英語で表すとなんと言うでしょうか?様々な表現方法があるので、それぞれの表現について詳しくご紹介していきます。
チャレンジド(challenged)
1991年にアメリカの日刊紙が使用始めた表現で、現在はメディアなどで頻繁に用いられている英語になります。「障がい」という言葉に根付いているネガティブなイメージを払拭するべく、挑戦する機会が与えられた人という意味を込めて用いられているのです。
しかし、カンサス大学の提唱している、障がい者を表す表現のガイドラインを基準にしたときに、表現が婉曲的であるという意見もあります。
ハンディキャップ(handicap)
「ハンディキャップ(handicap)」という表現は耳にしたことがあるのではないでしょうか?
この言葉は、リハビリテーション法504条など障害者関係法で用いられていた歴史を持ちますが、言葉の響が物乞いを連想させるという理由で、障がい者運動の中で反対する動きが見られています。
ディスアビリティ (disability)
Disabled peopleという表現も見られますが、人という言葉を先におく方が倫理的に良いのではないかという理由で、 People with disablities という表現が用いられるようになりました。また、法律用語として Indivisuals with disablities という言葉が使用されています。
セルフ・アドボケイト (self-advocait)
擁護を意味するadvocateを用いた表現方法で、直訳すると自分を擁護する人という意味になります。
「障害」という表記
「害」という言葉が常用漢字である理由で、「障害者」という言葉が頻繁に用いられてきました。
障害基本法の中にも、障害の表記という項目がありますが、明確な決まりはありません。
しかし政府が発行するような公式な書類には「障害」という表記が用いられています。
「障がい」という表記
いくつかの地方自治団体は「障害」に代わって「障がい」という表記を使用し始めています。特に札幌市は2003年から「障がい」という表記を用い始めました。
この表記の変化は「害」という文字からマイナスなイメージを連想させるからという考えから始まりました。
しかし、この動きに対して違和感を感じている障害者団体や人々が存在します。2014年には、社会が障壁の意味としての障害を作っており、この障害を取り除くのは社会の責任であるという考え方が示されました。
障害があるのは個人ではなく社会
「障害」というものは個人に存在するのではなく、社会に存在するという考え方が出てきたことにより、多文化共生の考え方がより一層必要になってきています。
社会に存在する固定観念やイメージが、ときに個人を傷つけてしまうことがあるのです。
「みんな違って当たり前」という考え方に対して相互理解が求められています。