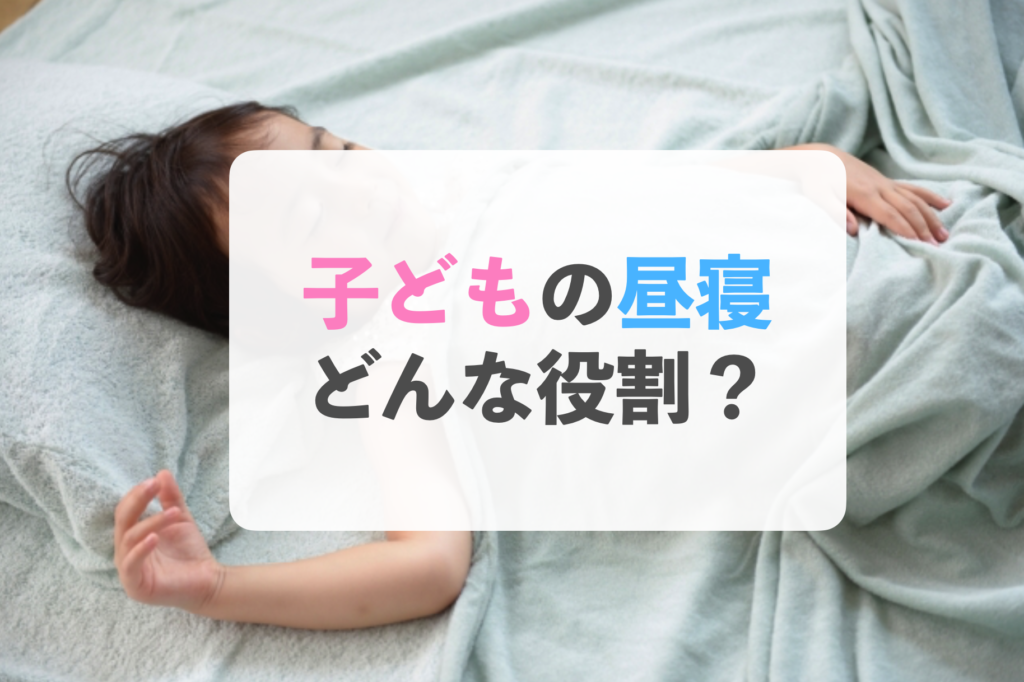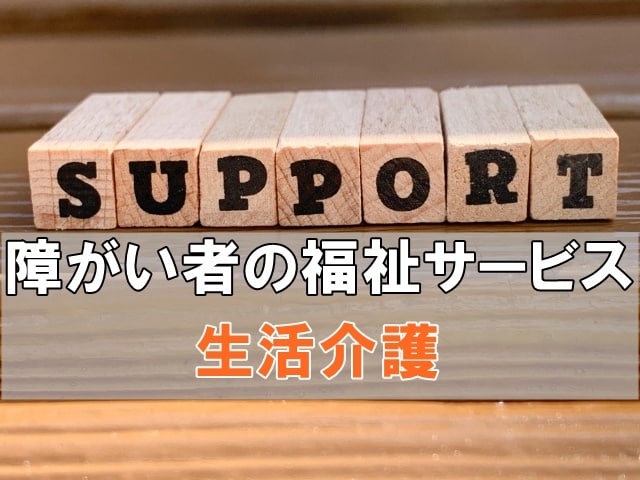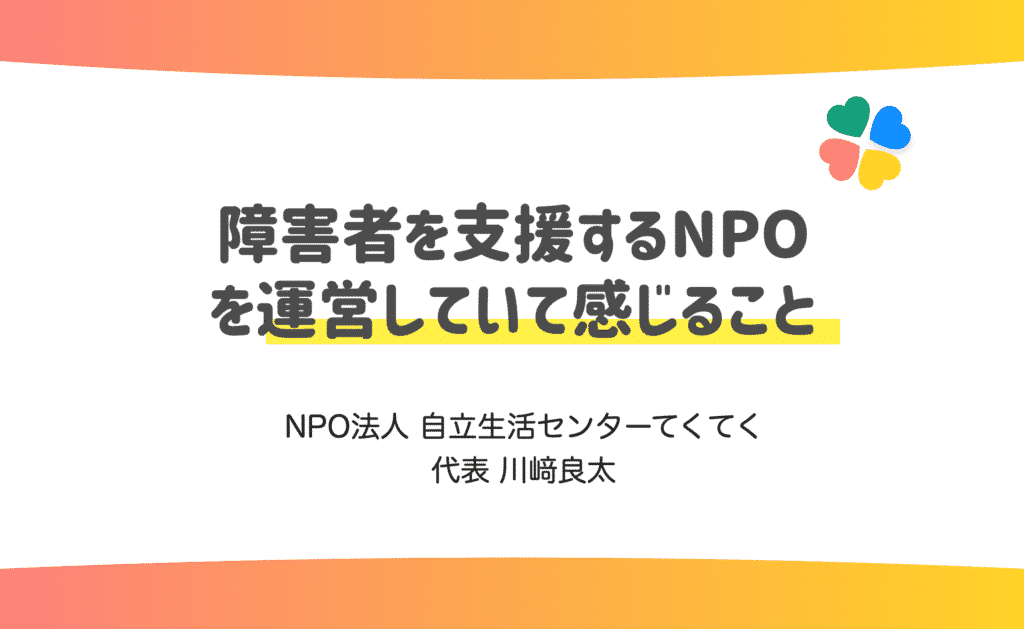普通に生活するだけでも身体に相当な負担がかかっている可能性が
私たち健常者は普段何気なく日常生活を過ごしています。
障がい児の場合も私たちと同じように学校に行ったり、家庭ではお風呂に入ったりなどの日常生活を過ごしているはずです。
ただ私たちが当たり前のように行っている動作でも、障がい児の場合は難しいことがあります。
一つ一つの動作が困難になりやすいので、健常者と比べて身体に相当な負担がかかっている可能性があるのです。
今回は、障がい児の生活における身体への負担について考えていきます。
実際どのくらい負担がかかっているのか?
私は以前脳性まひの方の心肺機能を簡易的に測定する評価を実施したことがあります。
PCIという評価法で、脳性麻痺理学療法診療ガイドラインにも提載されている評価法です。
~PCIの評価方法~
PCI・・・身体活動に伴う生理的なコスト。単位歩行距離あたりのエネルギー消費指数。
PCI(beats/m)= (歩行時心拍数ー安静時心拍数(beats/minute))/(歩行速度(m/minute) )
これをもとに実際にどのくらい負担がかかっているのか計測したところ、健常者と比べて倍以上の負担がかかっている可能性があることが分かりました。
ただこれは評価させていただいた人数が少なく、必ずしも皆脳性まひの方に当てはまるわけではありません。
それでも、ただ歩くという動作一つをとっても私たちよりも身体に負担がかかっている可能性は高いと思われます。
日常生活の動作を健常者と同じように考えるのは間違い
社会環境がどうしても健常者ベースなので、障がい児もそれに合わせて生活をしなければなりません。
ただ前述したように日常生活の一つ一つが障がい児にとってかなりの負担になってしまいます。
障がい児の日常生活を考えるときに、私たちのペースで考えることは間違いです。
時間がかかっても、うまく日常生活活動動作ができなかったとしても本人なりに頑張って活動しています。
そのことを理解して障がい児に関わっていきたいですね。
身体に負担がかかりすぎるとどうなる?
もし、身体に負担をかけすぎている状況が続くとどうなるのでしょうか。
あまりにも長期間身体に負担がかかると、逆に急速に身体機能が低下してしまうリスクがでてきます。
身体障がい児も私たちと同じように成人になってしばらくすると、代謝が落ち身体機能が低下していきます。
今まで身体に負荷をかけて頑張ってできていたことが、ある日急にできなくなってしまうこともあるのです。
そういったきっかけによって本人の意欲が低下してしまい、身体機能が低下しやすい状況になります。
私たちと同じように生活をしなければならないのではなく、本人なりの日常生活のペースで生活できる環境にしていかなくてはなりません。
まとめ
障がい児の身体機能は、思っている以上に普段の生活だけでも負担がかかってしまいます。
私たち健常者は障がい児を正常に合わせようと考えて接するのではなく、本人のペースで生活できるようにサポートしていくことが大切です。

出身地:宮崎生まれ鹿児島育ち
経歴:理学療法士/認定理学療法士(発達障害)
webライター
理学療法士として10年以上小児のリハビリに携わっています。
障がいをもった子どもたちとご家族の悩みはさまざまです。
少しでも悩みが解決できるようにこれからも情報を発信していきます!