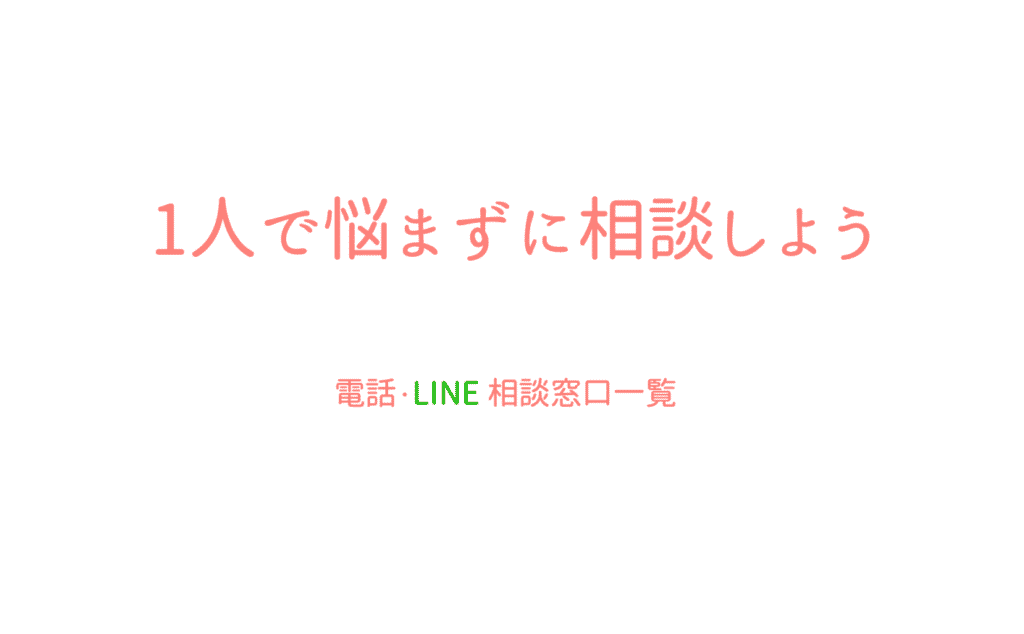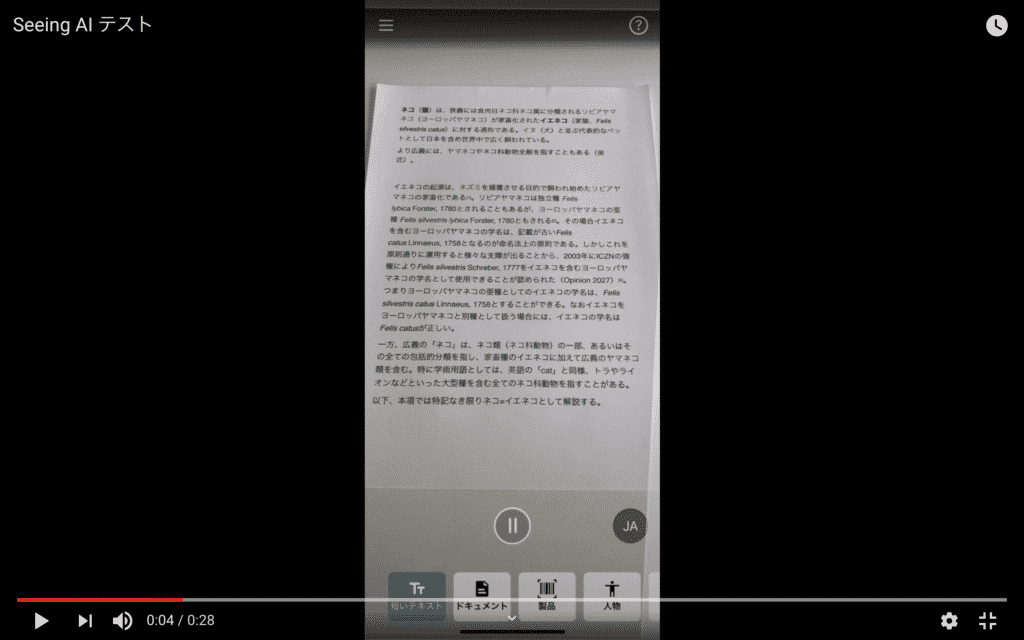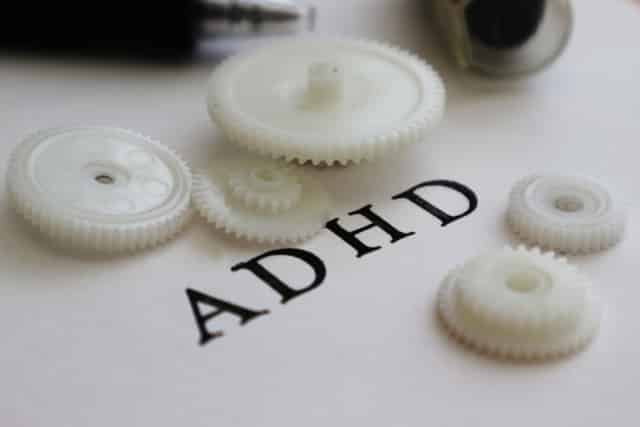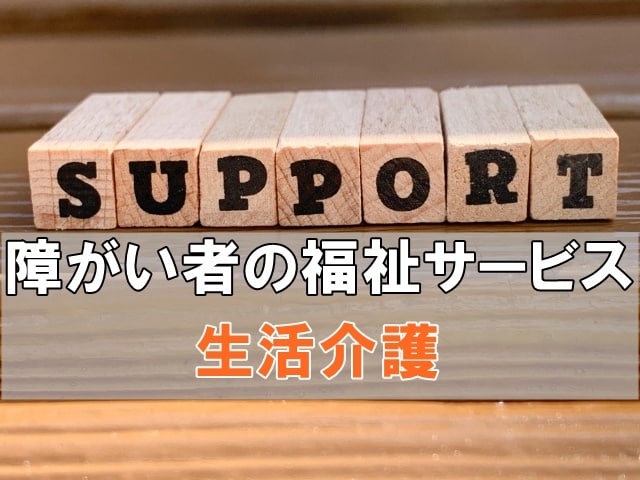
生活介護とは通所することで障がい者の身体機能を維持するためのサービス
学校に通っていた障がい児もいつかは卒業して障がい者になり、社会で生活していかなくてはなりません。
しかし、障がい児の場合は障がいの程度に個人差が大きく、いきなり社会で生活をするといっても難しいことが多いです。
そんな障がい者が学校を卒業してからも継続して機能を維持していくためのサービスの一つに「生活介護」があります。
今回は障がい者の福祉サービスの一つである生活介護について考えていきましょう。
生活介護とはどのような役割があるのか
生活介護とは、本人の状態に合わせて定期的に障がい者福祉施設などに通うことで、日常生活動作能力や身体機能などの維持を図るサービスです。
生活介護にも施設によって受けられるサービスがさまざまですが、基本的には施設のスタッフや他の通所者とコミュニケーションをとったり、季節ごとのいろいろな経験をしたりなどのサービスを受けることができます。
もっと具体的にサービスの内容をまとめていきますね!
・自宅では介助することが困難な場合などに入浴や排せつ、食事等の身体機能面で支援する
・介助者や本人が家事を行うことが困難な場合に家事全般の支援を行う
・介助者や本人に日常生活上の相談やアドバイスを通して支援する
・介助者や本人だけではさまざまな活動を行うことが困難な場合に季節ごとの活動や政策活動などの支援を行う
・身体機能の維持のために集団での体操などの支援を行う
なるほど。
学校を卒業したらこういった活動は家族や本人だけでは難しいですよね。
実際に学校に通っているときは機能が維持できていたけれども、卒業した途端に機能低下が起こることが多いです。
卒業してからの方が人生は長いですからね。
どういった方が生活介護のサービスを受けることができるのか
でも生活介護となっているので、介護が必要な状態でなければサービスは受けることが難しいのではないでしょうか。
まさにその通りで、日常生活上介護が必要な方が主な対象になります。
以下にまとめていきますね!
~生活介護の対象となる方~
・地域や施設において障がいにより日常生活上常時介護が必要な方
・年齢が50歳未満で障害支援区分が区分3以上である者
ただし障害者支援施設に入所して支援を受ける場合は区分4である必要がある。
・年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2以上である者
ただし障害者支援施設に入所して支援を受ける場合は区分3である必要がある。
・50歳未満で障害者支援施設に入所して支援を受ける方であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い区分の方のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者
まとめ
生活介護は、障がい者の日常生活能力を維持していくために重要な役割があるサービスです。
だれでも利用できるサービスではありませんが、常時介護が必要な障がい者とそのご家族の方にとっては重要なサービスなので、ぜひ活用してほしいですね。
まずは地域の生活介護の現状を把握することから始めてみましょう!

出身地:宮崎生まれ鹿児島育ち
経歴:理学療法士/認定理学療法士(発達障害)
webライター
理学療法士として10年以上小児のリハビリに携わっています。
障がいをもった子どもたちとご家族の悩みはさまざまです。
少しでも悩みが解決できるようにこれからも情報を発信していきます!