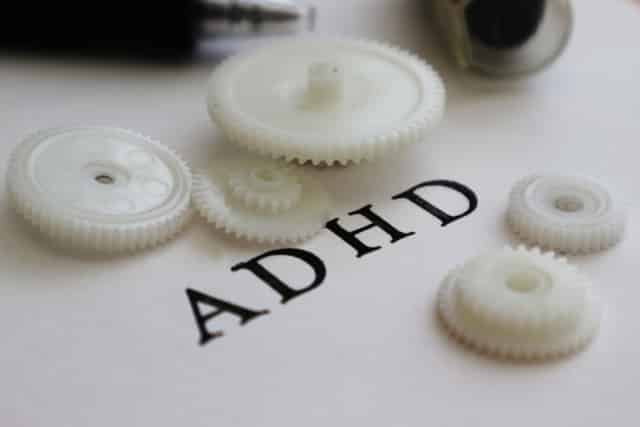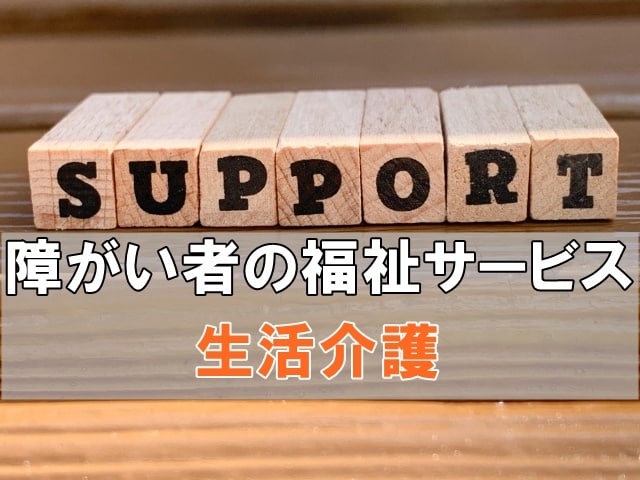歩行練習の目的は歩けるようになるためだけではない
歩行練習は多くの場面で行われる練習です。
小児分野においても同じで、将来実用的に歩くために歩行練習を行います。
ただ、身体的に重度な場合は移動手段として歩くということが難しいことも多いです。
そのため、いつまでも歩行練習をすることに意味があるのか?という質問を受けることがあります。
私の考えですが、歩行練習の目的は将来的に歩けるようになるためだけではありません。
今回は、障がい児における歩行練習の目的について考えていきます。
目的別の障がい児の歩行練習
まず実用的に歩けるようになる場合は、積極的に幼少期から歩行の経験を行ったほうが将来的にも継続して歩行を行うことが可能です。
多くは麻痺症状が軽度な場合や片麻痺の方などの場合が当てはまりますが、より歩きやすくするためには杖や歩行器を使用したほうが良いと思います。
一方、麻痺症状が手や足などの広範囲に及んでいる場合や身体的に重度な症状がある場合は自分で座ることさえ難しいことも多いです。
そういった場合の移動手段は主に手動の車椅子や電動車椅子ですが、自分の足で歩行を行う練習も大きな意味があります。
歩行練習の意義とは?
歩行練習の意義についてまとめていきます。
1、 変形・脱臼・側弯の軽減
脳性まひなどの身体障がい児にとって変形・脱臼・側弯といった影響は必ずと言っていいほど見られるものです。
こういった身体状態になりやすいのは、立つ姿勢や歩くといった動作が少ないことで発生しやすくなります。
身体障がい児にとって立って歩く練習は、骨に適度な刺激が入ることで変形や側弯といった身体症状の軽減につながります。
2、 歩行をすることで成功体験が経験できる
歩行練習の種類にもよりますが、歩行をするということは目的の場所に移動を行うということです。
自分で歩くことが難しいお子さんでも歩行練習をすることで自分の力で移動を行うことができます。
こういった経験はどんな補装具を使用しても自分で移動を行ったという成功体験になり、次の活動のステップにつながっていくはずです。
3、 少しの距離であっても目的をもって移動することが可能
前述したように歩くということは目的をもって移動を行うということです。
たとえ、少しの距離であっても目的の場所に移動を行うということは日常生活の中で必要になってきます。
(例)
家の中でベッドからトイレに行くときに歩行器を使用する など
まとめ~歩行を積極的に日常生活に取り入れていこう!~
歩行を行うということは、将来実用的に歩くことが難しい子どもたちにとってあまり意味がないのではないかと思われるかもしれません。
でも歩行を行うことにはさまざまなメリットがあり、必ず将来につながっていくはずです。
必ずしもすべての子どもたちに歩行が当てはまるわけではありませんが、積極的に歩行する機会を日常生活に取り入れていきましょう!
※すべての身体障がい児に歩行練習が適応になるわけではありません。歩行が難しくても移動を行う手段は様々なものがあります。一つの考えとして理解していただけると幸いです。

出身地:宮崎生まれ鹿児島育ち
経歴:理学療法士/認定理学療法士(発達障害)
webライター
理学療法士として10年以上小児のリハビリに携わっています。
障がいをもった子どもたちとご家族の悩みはさまざまです。
少しでも悩みが解決できるようにこれからも情報を発信していきます!