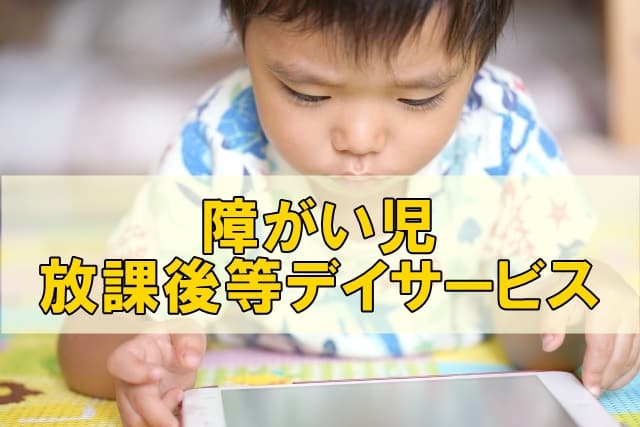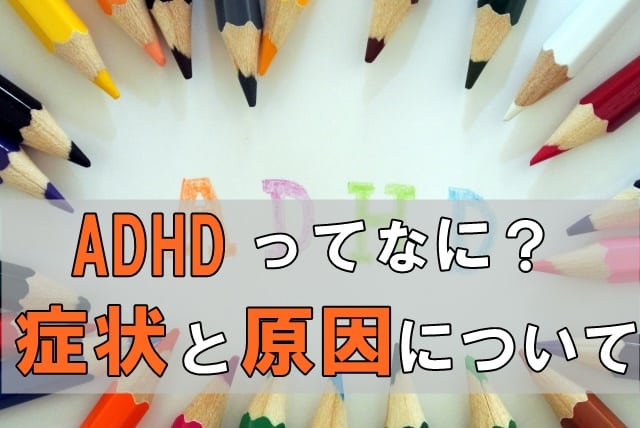
ADHDは発達障害の一つ
最近見た目でははっきりと障がいがあると分かりにくいけれども、集団生活で問題を抱える子どもたちが増えてきています。
これらの障がいはいわゆる「発達障害」という障がいであり、その原因と症状を理解することで本人の生きづらさを少なくすることが必要です。
その発達障害の中でも「落ち着きがない」「集中できない」「忘れ物が多い」といった症状が見られる『注意欠如・多動症(以下ADHD)』という疾患があります。
今回は、そんなADHDの症状と原因について考えていきましょう。
ADHDとはどのような疾患なのか?
ADHDは、就学前の子どもの時期から症状が目立つことが多く、その段階で診断をされるケースがほとんどです。
ただ、中には大人になるまで診断されず社会にうまく適応することが難しいといったケースもある場合も・・・。
症状は名前を見ても分かる通り3つのタイプに分けられます。
・注意がそれやすく、不注意が目立つタイプ(不注意型)
・じっとしていることができず、衝動的に動いてしまうタイプ(多動・衝動性型)
・不注意と多動・衝動性型が混在しているタイプ(混合型)
なるほど。
ADHDの症状は一つではないのですね!
ADHDの原因とは?
ADHDははっきりとした原因は解明されていません。
ただ、生まれたときから脳に異常が見られることが関わっているのではないかと言われています。
その脳の中でも前頭前野という思考・判断・注意などといった情動性・精神面を司る部分の障がいであることも分かってきました。
ただ、なぜ前頭前野に障がいが起こってしまうのかはよく分かっていません。
ADHDは育て方が原因で発症するわけじゃないのか。
生まれたときからの脳の異常が原因かもしれないということですね。
どのような症状が見られるのか
ADHDというと落ち着きがなくて動き回っているような印象があるかもしれません。
確かに落ち着きがないという症状も見られますが、他にも症状が見られ3つのタイプに分類されます。
それぞれの症状についてまとめていきますね。
~不注意型の特徴~
・身の回りのものを片付けることが苦手
・保育園などの集団活動で与えられた課題に集中できない
・忘れ物が多かったり、ものを紛失してしまったりする
・相手の話を聞いているようで聞いていない(理解していない)
・最後まで活動をやり遂げることが難しい など
~多動型の特徴~
・集団活動や授業中にじっと座っていられない
・ショッピングセンターなどの刺激が多い場所で走り回ったり、迷子になったりする
・静かにテレビを見たり、本を読んだりすることができない
・好きなことに集中しすぎてしまい、周囲の危険に気づけない
・静かにしなければならない場面でも大きな声でおしゃべりをしてしまう
・起きてから寝るまで常に動き回って落ち着きがない など
~衝動型の特徴~
・我慢しなければならない場面で我慢することができない
・我慢できなくて相手に手をだしてしまう
・相手の意図を読み取ることが難しいので、話を聞かず自分の話ばかりしてしまう
・自分のものでもないのにおもわず目についたものを使ってしまう
・やりたいことばかり優先してしまう
・今やるべきことを後回しにしてしまう など
ADHDって落ち着きがないだけかと思っていました。
特に不注意型はわかりにくいので、子どもが困っていてもわからないかもしれませんね。
まとめ
ADHDは、タイプによって見た目からはほとんど障がいがあると分かりません。
そのため、周囲の人たちの理解を得ることが難しい疾患です。
ADHDの症状と原因について理解することで、子どもたちの困り感に寄り添えるようにしていきましょう!

出身地:宮崎生まれ鹿児島育ち
経歴:理学療法士/認定理学療法士(発達障害)
webライター
理学療法士として10年以上小児のリハビリに携わっています。
障がいをもった子どもたちとご家族の悩みはさまざまです。
少しでも悩みが解決できるようにこれからも情報を発信していきます!