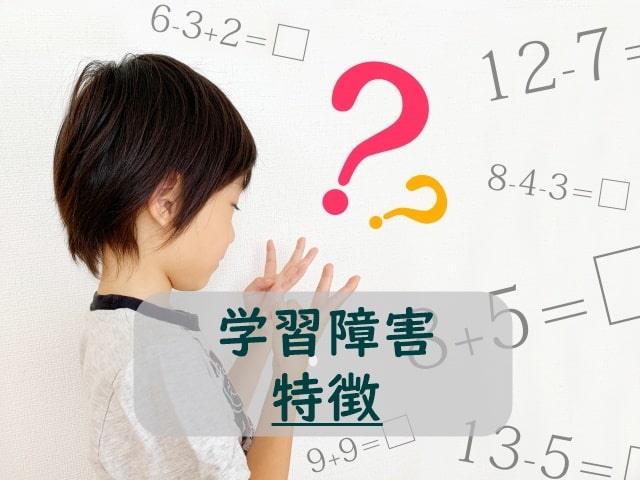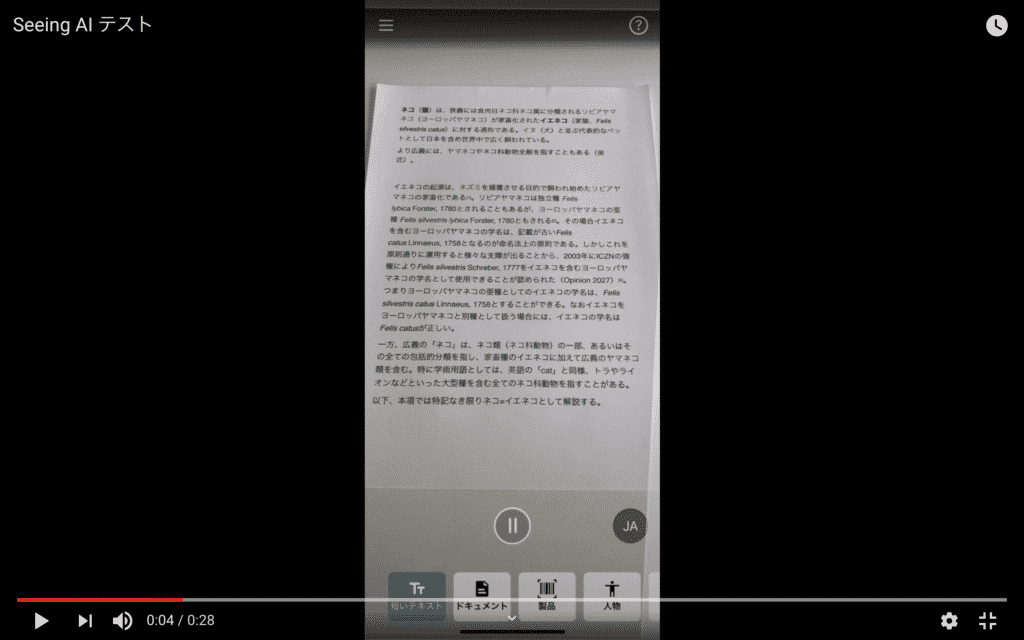目次
座位保持装置は座ることが難しい場合に必要な補装具
みなさんは、「座位保持装置」という補装具を聞いたことがあるでしょうか。
なんだか難しそうな名前ですが
簡単に言うと座ることが難しい方のための座椅子のようなものです。
車いすでは座ることが難しい場合は
ほとんどの方が座位保持装置を利用しています。
ただ、座位保持装置と一言で言っても
種類がいくつかあってその機能もさまざまです。
今回は、座位保持装置という補装具は何か?ということについて紹介していきたいと思います。
座位保持装置は、自分で座ることが難しい方にとっては必ず必要な補装具
重症心身障がい児の子どもは、自分でからだを支えることが難しいので座ることも大変です。
でも、座ってからだを起こすことができたらいろいろな可能性が広がりますよね!
どうしたら座ることができるのでしょうか?
そんなときは「座位保持装置」という補装具が役に立ちます。
いったいどんな補装具?と思われるかもしれませんが
座ることが難しい方が座る姿勢を保持するために必要な補装具です。
つまり、座りやすくするための椅子みたいなものですね!
座位保持装置ってなんだか難しい名前ですね・・・
でも、子どもたちの中には自分でからだを起こすことも難しいことも多いですが、どんな状態でも座ることができるのですか?
座ることでからだに悪影響が及ぶ場合は使用することをひかえます。
でも、座ることでメリットもたくさんあるので
重症心身障がい児にとっても重要な補装具だと思います。
座位保持装置に座ることによってどんなメリットがあるのか?
自分で座ることが難しいなら
無理して座る必要はないのではないでしょうか?
確かにそうですね。
でも、自分で座ることが難しいからといって
ずっと寝たままの姿勢だと本人の意欲がなくなってしまいます。
座った姿勢は、頭を起こして周りを見渡すことができますよね?
これだけでも目線が変わり、さまざまな意欲が引き出されます。
言われてみれば普段私たちは当たり前のように
頭を起こして生活していますね。
重症心身障がい児の子どもたちにとって
座位保持装置はさまざまな意欲を引き出すために必要なものなのですね。
そうです。
座ることで手の操作も行いやすくなりますしね。
健常者にとって座ることはなんでもないことですが
重症心身障がい児にとっては座ること自体が困難です。
座位保持装置をうまく使って生活を豊かにしていきたいですね!
自分で座ることができれば
介助をする側も楽になりますね!
いろいろ教えてくれてありがとうございました。
これだけは知っておこう!座位保持装置を使うときの3つのメリット
・ただ座るために使用するのではなく、座ることが難しい方の意欲を引き出す
・頭を起こした状態は、目線が変わるので子どもたちの発達が促されやすい・学校や家庭において周囲とコミュニケーションをとるためにも必要
座るための補装具には他にも車いすがありますが
座位保持装置はより座りやすくするための補装具です。
そのため、車いすでは座ることが難しい方でも
座位保持装置ならば頭を起こした状態で座ることが可能になります。
もちろん、介助者が支えて座ることもできますが
いつも介助することは難しいですし負担も大きいですよね。
座位保持装置をうまく利用して
家庭や学校でも快適に生活できるようにしていきましょう!

出身地:宮崎生まれ鹿児島育ち
経歴:理学療法士/認定理学療法士(発達障害)
webライター
理学療法士として10年以上小児のリハビリに携わっています。
障がいをもった子どもたちとご家族の悩みはさまざまです。
少しでも悩みが解決できるようにこれからも情報を発信していきます!