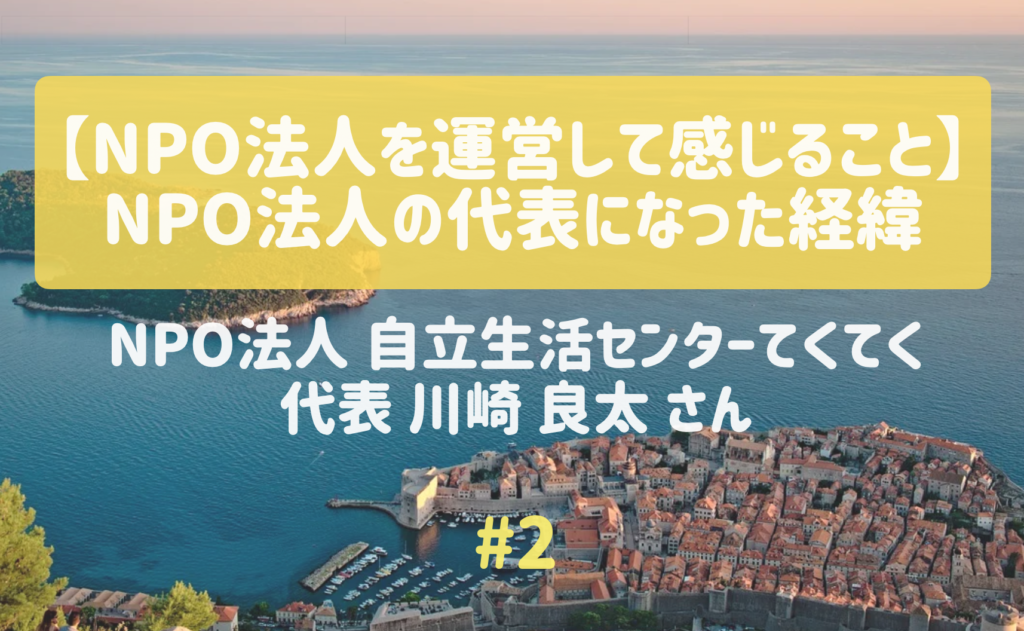はじめに
障がいをもった子どもたちのリハビリの中で、ご家族自身もからだに不調を感じることがあります。
特に子どもがまだ小さいときは、何をするにしても子どもを抱っこして移動しなければなりません。
そこで、今回はなぜ育児をしているときは肩こりになりやすいのかということについて紹介していきたいと思います。
育児は思っている以上に大変
子どもが生まれるまでは肩こりになったことなんてなかったのに、子どもを毎日抱っこしているせいか最近肩こりがひどいです。
でも、子どもを抱っこしないと何もできないし・・・
どうしたらいいのかなあ・・・
育児は思っている以上に大変ですよね。
特に子どもが小さいときは、何をするにも子どもを抱っこしなくてはなりません。
そのため、肩にかかる負担は相当なものです。
できるだけ肩に負担がかからないようにしなくてはなりませんね。
でも、毎日忙しくて肩に負担がかからないようにするなんて無理です。
そうですよね。
実は育児自体が肩こりの原因ではないのです。
最近は共働き世帯が増加してきて女性も働きながら家事をこなさなければなりませんよね。ただでさえ忙しい毎日にさらに育児という不規則な生活が加わります。
それに何をするにしてもうつむき加減になってないですか?
確かに仕事もデスクワークですし、家事も掃除や料理など下を向いてやるものばかりですね。
それに育児も授乳や抱っこなどうつむく姿勢が多いです。
そのうつむく姿勢が肩に負担をかけているのです。
実は育児によって急に肩こりになったわけじゃなく、普段の生活にさらに育児が加わり肩により負担をかけているということですね。
肩こりを予防するためには?
肩こりの原因は分かりましたが、どうすれば肩こりを予防することができますか?
肩こりの原因は主に長い期間同じ姿勢が続くことで痛みが出てきます。
そのため、まず普段からの姿勢を改善しましょう。
以下に簡単な体操を紹介します。

①胸の前で両手の手のひらを合わせて、息を吸いながら上に向けて挙上していきます。
☆このときに胸を張るようにしてください。
②合わせていた手のひらを外側に向けます。その後息を吐きながら肘を曲げて腕を左右に下ろしていきます。
☆真横でなく少し後ろの方を意識しながら腕を下ろすことで、肩甲骨の動きが引き出されます。
③これを3セット繰り返す
また、ラジオ体操も効果的です。
時間がなくても数分で終わるのでおすすめです。
肩だけではなく、腰や足の運動にもなりますよ!
ぜひやってみてくださいね。
普段からの姿勢を改善するだけで肩こりは予防することができるのですね。
日常の姿勢から気をつけるようにしてみます。
それから、最近は父親も積極的に育児や家事をする家庭が増えてきましたが、それでもまだ母親に集中してしまいがちです。
共働きであるならば家事・育児を均等に分担するだけでも肩こりになるリスクを抑えることができますよ!
まとめ
・育児によって肩こりが見られるのではなく、普段からの姿勢が大きく影響する
・日常生活の負担が集中しないように家族で分担して家事・育児を行うことが大事
・うつむく姿勢は肩に負担をかけやすい
・うつむく姿勢が続くことで筋肉がかたまり、肩こりの原因になる
・肩の運動をするときには肩甲骨を意識する

育児は慣れていないこともあり、子どもを抱っこするだけでもからだに負担がかかります。
ただでさえ共働きが増えているのに、家事も育児もやらなければならなくなると知らない内に身体的にストレスがかかってしまいます。
育児が大変であることに変わりはありませんが、普段の姿勢を改善するだけでも肩こりは予防することができると思います。
肩こりに悩む方たちにとって少しでも参考になれば幸いです。
ご質問はこちらから
下記のボタンからこの記事を書いた認定理学療法士の先生に無料で質問をすることができます。質問の答えはEASIERのTwitterにて公開します。

出身地:宮崎生まれ鹿児島育ち
経歴:理学療法士/認定理学療法士(発達障害)
webライター
理学療法士として10年以上小児のリハビリに携わっています。
障がいをもった子どもたちとご家族の悩みはさまざまです。
少しでも悩みが解決できるようにこれからも情報を発信していきます!